中国のバーコード国番号は「690〜699」|製品の見分け方と注意点を解説
バーコードの先頭3桁はGS1の国番号(プレフィックス)の目安で、中国は「690〜699」が割り当て範囲です。この記事では、国番号とバーコードの関係、見分け方の手順、誤解しやすいポイント、購入時のチェックリストまでをわかりやすく整理します。なお、国番号は原産国を保証するものではありません。発行主体(GS1の各国組織)を示す目安で、製造地や最終組立地とは一致しないことがあります。

中国のバーコード国番号とは?
国番号とバーコードの関係(直感的にわかる説明)
一般的な消費財のバーコードは EAN-13(日本名:JANコードを含む)です。13桁を「住所」にたとえると、次のように読むと直感的です。
- 先頭3桁=国番号(プレフィックス) … 郵便番号の“国”部分のようなもの。どのGS1(バーコード発行団体)の管轄かを示す目安。
- 続く数桁=企業コード … その国(管轄)の中での「会社の番地」。発行団体が企業に割り当てる識別子。
- その次=商品コード … 会社の中での「部屋番号」。個々の商品に固有の番号。
- 最後の1桁=チェックデジット … 読み取りミスを防ぐための「検査番号」。合っていれば正しく読めたサイン。
つまり、EAN-13は「国番号/企業コード/商品コード/チェックデジット」という4ブロックでできています。国番号は原産国の証明ではなく、そのバーコードを誰の管轄で発行したかの目安です。
例(見やすくスペースを入れた表記)
690 1234 567890 5
「690」=国番号(中国の範囲)、
「1234」=企業コード(中国GS1の会員企業に割り当て)、
「567890」=商品コード(企業が自社で付番)、
「5」=チェックデジット(検査用の1桁)。
チェックデジットは何をしている?(超ざっくり)
左から奇数桁と偶数桁に分け、偶数桁を3倍して全部足し、合計を10の倍数にするために必要な数が最後の1桁になります。スキャナはここを計算して一致するかを確認しているため、にせの番号や読み取りミスを検知しやすくなります。
JANとEAN-13の関係
日本で「JANコード」と呼ぶものは国際規格のEAN-13に準拠した表記です。日本のプレフィックスは「45」「49」(より厳密には450–459/490–499帯)などが使われます。同様に、米国のUPC-A(12桁)はEANに相互変換できます。
中国に割り当てられている範囲「690〜699」
GS1が各国・地域の発行団体に割り当てるプレフィックス(国番号帯)のうち、中国には690〜699が配分されています。したがって、先頭3桁が「690〜699」なら中国のGS1管轄で発行されたコードという目安になります。
ただし重要な注意点として、国番号=原産国の保証ではありません。たとえば日本のブランドでも海外製造の製品があり、逆に海外ブランドでも日本のGS1経由で番号を取得している場合があります。原産国を確認したいときは、原産国表示・製造所固有記号・保証書や型番・正規販売チャネルの情報とあわせて判断しましょう。
参考:プレフィックスの例(覚えやすい代表のみ)
日本:45/49、韓国:880、台湾:471、香港:489、中国:690–699。
※あくまで「発行団体の管轄の目安」。原産国の証明ではありません。
バーコードで中国製品を見分ける方法
先頭3桁をチェックする手順
- パッケージ裏面や底面のEAN-13を探す。印刷が薄い場合はスマホのライトで照らすと読みやすい。
- 先頭3桁を確認し、「690〜699」に該当するかをチェックする。該当すれば中国プレフィックスと判断できる。
- 完全な判定のために、企業名やブランド表記、型番も合わせて確認する。国番号だけで原産国は断定しない。
食品・日用品などに印字されるバーコードの例
食品の外箱では高精度印刷、日用品ではラベルシールの場合が多いです。箱の側面や底面など見つけにくい位置にあることもあるため、複数面を確認しましょう。
スマートフォンアプリを利用した読み取り(確実に読める方法)
- Googleレンズ(iOS/Android 共通):Googleアプリ内のレンズから、バーコードや商品を読み取り→ウェブ検索や価格情報にジャンプできます。Chromeのレンズでもバーコード専用の撮影が可能です。
参考:Google レンズ案内ページ / Chromeでレンズを使ってバーコードをスキャン。 - ShopSavvy(iOS/Android):カメラでJAN/EAN/UPCのバーコードを直接スキャンし、国内外の多数小売の価格を比較できる定番アプリ。価格履歴や在庫もチェックできます。
参考:公式アプリ紹介 / App Store / Google Play。 - GS1系の専用アプリ(業務寄り):医療や流通で使うGS1 DataBar/GS1-128などの高度な記号にも対応する公式系アプリがあり、現場での確認に向きます(一般消費者の買い物用途というより業務用途)。
参考:GS1 Healthcare Barcode Scanner(案内) / App Store。
標準カメラでできること(QR中心)と、できないことの切り分け
- iPhone:カメラ/コードスキャナでQRコードは標準対応。製品バーコードを検索連動まで行いたい場合は、Googleアプリのレンズや専用アプリの併用が実用的です。参考:Apple公式:QRコードをスキャン。
- Android(Pixel/多くの機種):標準カメラやGoogleレンズでQR対応。製品バーコードはレンズで検索か、ShopSavvy等の専用アプリが確実。参考:Googleカメラ:QRのスキャン。
- Samsung Galaxy:カメラ/クイック設定/Bixby Vision等でQRが読めます。製品バーコードの検索はレンズ(Googleアプリ/Chrome)や専用アプリを推奨。参考:GalaxyでQRコードをスキャンする方法。
使い方のコツ(失敗しないために)
- 照明とピント:暗い場所では読み取り精度が落ちます。スマホのライトを点け、バーコード全体がフレームに収まるように少し離れてピントを合わせてから撮影すると成功率が上がります。ShopSavvyのヘルプでも、カメラでレーザーの代わりに撮像するためコツが必要と案内されています。参考:ShopSavvyヘルプ。
- クロスチェック:アプリにより表示データベースが異なります。レンズ+ShopSavvyの二段構えにすると、ヒット率と正確性が上がります(価格比較も可能)。
- プライバシー:位置情報・カメラ・写真へのアクセス許可は必要最小限に。不要な権限を求めるアプリは避け、公式/大手のアプリを選ぶと安心です(Google/Appleの公式ヘルプでQR対応が明記)。
中国のバーコード国番号に関する注意点
必ずしも原産国を保証しないのはなぜ?(やさしい説明)
先頭3桁の「国番号(プレフィックス)」は、製品がどの国で作られたかではなく、そのバーコードをどの国のGS1(発行団体)が管理しているかの目安です。たとえると、バーコードは「住所ラベル」のようなもの。先頭3桁は「どこの窓口で住所ラベルを発行したか」を示すだけで、実際の工場がどこにあるかまでは教えてくれません。
- 例1:日本ブランド × 海外工場(OEM)
設計やブランドは日本、製造は中国の工場。バーコードの番号は、日本のGS1から会社が番号をもらえば先頭は「45/49」などになりますが、中国のGS1で番号を取得すれば「690〜699」から始まることもあります。つまり、国番号は「発行窓口」を示すだけです。 - 例2:海外ブランド × 多国籍サプライチェーン
部品は国A、組立は国B、最終検品と梱包は国Cということも珍しくありません。プレフィックスだけで「原産国C!」とは断定できません。 - 例3:同じ商品でも流通先で違うバーコード
大手小売が自社の在庫管理のために、独自のJANコード(自社で発番したバーコード)を貼るケースがあります。結果として、同一商品でもプレフィックスが異なることがあります。
ポイント:プレフィックスは「どのGS1に加入して番号をもらったか」の手がかり。原産国の証明書ではないと覚えておきましょう。
輸入業者や流通で番号が変わるケース(具体例で理解)
- 輸入事業者の貼り替え:海外製品に輸入者が自社JANを付け替え。店頭で見ると、メーカー公式のバーコードとは別番号になっていることがあります。
- PB(プライベートブランド)化:同じ工場の製品を、小売独自ブランドとして販売。小売側のバーコードが付くため、元メーカーのバーコードと一致しないことがあります。
- 並行輸入:正規代理店ルートとは別の経路で輸入。代理店発番のコードと、並行輸入品のコードが異なる場合があります。
かんたんチェックリスト(バーコードだけに頼らない)
- 原産国表示を確認:パッケージの「Made in 〜」や原産国表記は、バーコードとは別の公式情報です。
- 型番・ロット・保証書の整合:箱・本体・保証書の型番が一致しているか。不一致は要注意。
- 正規販売チャネルか確認:公式EC・正規代理店の案内があるか。返品・保証の有無もチェック。
- 読み取りアプリで裏取り:先頭3桁に加え、企業名・商品名の表示があるかを確認。内容が貧弱な場合は別アプリでもクロスチェック。
- 印刷品質:バーの太さが不均一/数字とバーの長さが合わない/読み取り不能が続く → 不自然。購入を急がず再確認。
よくある質問(Q&Aでサクッと理解)
- Q:先頭が「690」なら絶対に中国製?
A:いいえ。中国のGS1経由で番号を取得した目安に過ぎません。製造国の確定は、原産国表示やメーカー情報で。 - Q:同じ商品なのにプレフィックスが違うのは偽物?
A:必ずしも偽物ではありません。輸入業者の貼り替えや小売独自バーコードで異なることがあります。型番や保証の整合で確認を。 - Q:バーコードだけで真贋判定できる?
A:できません。バーコードは手がかりの一つ。販売元・製品情報・保証の有無とセットで判断しましょう。
まとめ:「690〜699」は中国プレフィックスの目安ですが、原産国の証明ではないため、原産国表示・型番・販売チャネル・保証をセットで確認するのが安全です。
中国製品を購入する際のチェックポイント
信頼できる販売元・ブランドの確認
- 正規販売チャネルかを確認。公式ECや正規代理店の記載があるかチェックする。
- 製品の型番・ロット・保証書が整合しているかを確認。記載の矛盾は注意サイン。
- 初期不良や返品ポリシーが明記されているかを確認。サポート連絡先もあわせてチェック。
偽造バーコードや不正表示への注意
- 印刷がにじむ、線の太さが不均一、読み取り不能などは不自然。複数の面に同じバーがあるか確認する。
- バーの下の数字列とバーの長さが一致しない、検査アプリでチェックデジットが不正と出る場合は要注意。
- 不審な場合は、メーカーの公式サイトで型番を検索し、写真や仕様と一致するかを確認する。

まとめ|中国製品のバーコードは「690〜699」を目安に確認
690〜699は中国のGS1プレフィックスです。先頭3桁を確認し、必要に応じて読み取りアプリや公式情報で裏取りしましょう。重要なのは、国番号は原産国の保証ではないという点です。販売チャネルや製品情報の整合性を合わせて確認すれば、安心して購入判断ができます。
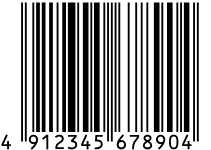


コメント